|
|
|
| 慈照院〔相国寺〕 (京都市上京区) Jisho-in Temple |
|
| 慈照院 | 慈照院 |
 |
 |
 山門  山門  山門「桂宮御牌所」  山門  山門  延段   枯山水式庭園、山門入って右にある枯山水式庭園。   庫裏  庫裏   玄関  本堂   本堂東の庭園  庭園、樹齢300年以上という陸船松(りくせんまつ)  庭園、大きな平石、礼拝石様  庭園、手前から本堂の縁と亀甲形の敷瓦(磚)、縁石、溝石(雨落ち)、苔地  庭園、枯山水式  枯滝石組     本堂から見える桂宮西ノ墓地に立てられている宝篋印塔2基。  庭園、借景としての比叡山の山頂、現在の眺望は失われている。   書院南の路地庭、飛石は弧を描いて茶室にまで延びている。  手水鉢  茶室「頤神室(いしんしつ)」  蹲  胡蝶侘助、樹齢300年。春の彼岸に満開になる。  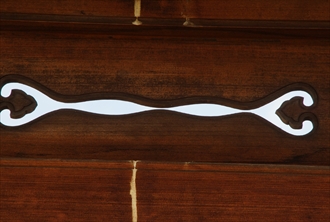  【参照】寺に隣接している桂宮東ノ墓地、宝篋印塔。   【参照】桂宮西ノ墓地、宝篋印塔。    朝鮮通信使ゆかりの地の駒札  【参照】初来日400周年に再現された朝鮮通信使の行列、四条大橋(2007年11月3日)、朝鮮通信使は江戸時代、1607年-1811年まで12回、400-500人の一行が漢城(ソウル)から対馬、京都、江戸へと向かった。時に対馬止まり、京都止まり、また日光まで行くこともあった。 |
相国寺の北西にある相国寺塔頭・慈照院(じしょう-いん)は、足利義政の墓所(香火所)になっている。寺号は義政の法号「慈照院」に因む。 臨済宗相国寺派。本尊は十一面観世音菩薩。 ◆歴史年表 室町時代、1405年頃、相国寺13世・在中中淹(ざいちゅう-ちゅうえん)が創建したという。当初は「大徳院」と称した。 1428年、在中の没後、その塔所になる。 1490年、第8代将軍・足利義政の没後、当初、その遺骨は相国寺塔頭・大智院に安置されている。相国寺の塔頭は足利家歴代将軍の位牌所になっていた。義政の法号は、「慈照院殿准三宮贈大相国一品喜山道慶大禅定門」であり、焼香を行うための香火所の寺は、院名を法号としていた。だが、「慈照院」と改めることに大智院門徒の反対があったという。(『蔭涼軒日録』)。このため、同年、勅命、蔭涼軒院主・亀泉集証の尽力により、香火所は大徳院(塔主・景徐周麟)に決まり、寺号も「慈照院」に改められた。以後、義政の菩提所になり、遺骨も当院に遷された。(「大徳院被成慈照院最初時冝事」)。さらに、大徳院(塔主・景徐周麟)は、1491年に亡くなった8代将軍・足利義視の香火所だったため、その遺骨は大智院に遷されている。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、相国寺朱印高より30石1升あまりを配されていた。 江戸時代初期、桂宮家菩提所になる。 1629年、桂宮は御学問所を当院境内に建てる。 1632年、7世・仏性本源国師・昕叔顕啅(きんしゅく-けんたく)は、桂宮初代・智仁親王、2代・智忠親王との親交により、桂宮の御学問所(現在の書院・棲碧軒(せいへきけん)が下賜される。 1671年、智仁親王妃・常照院殿の遺命により、尾張徳川が現在の本堂を建造し桂宮御霊牌殿とした。 1707年、第113代・東山天皇より宸殿一宇を贈られる。 宝暦年間(1751-1764)、本堂が増築されたという。 1763年、桂宮旧殿を贈られ、移築拡張し、広幡家は玄関などを改築した。 近代、1883年、桂離宮の園林堂に安置されていた八条宮・桂宮家の位牌が慈照院に遷された。(『桂宮日記』) 現代、1982年、住職が土蔵より朝鮮通信使が贈った襖に貼られた漢詩文、水墨画を発見した。 ◆在中 中淹 南北朝時代-室町時代前期の臨済宗の僧・在中 中淹(ざいちゅう-ちゅうえん、1342-1428)。詳細不明。男性。能登(石川県)の生まれ。南禅寺の竜湫周沢の弟子になり、後に比叡山に上り受戒し、諸国遊学後に、竜湫の法を嗣ぐ。相国寺13世、天龍寺、南禅寺住持を歴任した。晩年、南禅寺の瑞雲庵に退隠した。87歳。 ◆景徐 周麟 室町時代中期-後期の臨済宗の僧・景徐 周麟(けいじょ-しゅうりん、1440-1518)。男性。道号は景徐、諱は周麟、号は宜竹(ぎちく)、半隠(はんいん)、対松(たいしょう)など。近江(滋賀県)の生まれ。父・大舘持房(おおだち-もちふさ)、母・赤松則友の娘。5歳で相国寺に入り、夢窓派の相国寺・用堂中材(ようどう-ちゅうざい)の法を嗣ぐ。詩文を瑞渓周鳳、希世霊彦、横川景三、桃源瑞仙に学ぶ。応仁・文明の乱(1467-1477)で、1467年、近江・永源寺に逃れる。景徳寺、1495年、等持寺、82世・相国寺の住持、1496年1497年-1500年、鹿苑院主になり僧録司になる。1508年、相国寺に移り慈照院に退隠し、宜竹軒で亡くなる。当院に葬られた。著『翰林葫蘆(かんりんころ)集』、日記『等持寺日件』など。79歳。 五山文学僧。詩文に秀で、学僧として知られた。 ◆足利 義政 室町時代中期-後期の室町幕府8代将軍・足利 義政(あしかが-よしまさ、1436-1490)。男性。幼名は三寅、三春、初名は義成、法号は慈照院、東山殿。京都の生まれ。父・6代・足利義教(よしのり)、母・日野重光の娘・重子(しげこ)の次男。7代将軍・義勝の同母弟。1441年、嘉吉の乱で父・義教が暗殺され、1443年、兄・義勝も夭死し、9歳で家督を継ぐ。以後、擁立した宿老の細川持賢、畠山持国、山名持豊らが政治の中心になる。1446年、第102代・後花園天皇から義成と命名され、従五位上に叙任された。1448年、後左馬頭、1449年、元服し、14歳で室町幕府8代将軍に就いた。参議・左中将を兼ねる。1453年、義政と改名した。1455年、正室になった日野富子との間に嫡子はなかった。1459年以後、寛正の大飢饉が起こる。1460年、左大臣になる。1461年、梅津山荘の建築を行う。1464年、准后宣下を受けた。弟・義視(よしみ、義尋)を後継者にした。1465年、実子・義尚の誕生により、将軍職を巡る抗争になる。富子は山名宗全と結び義視の排斥に動く。義政側の山名宗全と、義視側についた細川勝元、さらに管領家の斯波、畠山氏、諸大名を巻き込んだ応仁・文明の乱(1467-1477)になる。1473年、義政は8歳の子・義尚に譲り隠棲した。以後、実権は富子が握る。1483年、京都東山の山荘に銀閣を造り移り住む。1485年、出家し、喜山道慶と名乗る。最晩年、銀閣寺の造営に固執した。1489年、後継者・義尚は24歳で早逝する。義政は一時、政務に復帰した。1490年、急逝した。55歳。 幕府の財政難、飢饉疫病の蔓延、土一揆の頻発もあり、在職中13回も徳政令を発布した。東山に山荘を造営し銀閣寺(慈照寺)、東求堂を建てた。学問、芸術、和歌などに優れ、猿楽・茶の湯・絵画を好む。音阿弥、善阿弥、小栗宗湛、相阿弥らを育て、東山文化を形成した。死の直前まで、観音殿の内装について指示を出したという。その完成を見ることはなかった。 ◆仏性 本源 国師 江戸時代の臨済宗の僧・仏性 本源 国師(ぶっしょう-ほんげん-こくし、 ?-? )。男性。昕叔顕啅(きんしゅく-けんたく)とも称した。父・日野輝資。有節瑞保に師事、法を嗣ぐ。相国寺を経て、鹿苑院の僧録司、第108代・後水尾天皇により召され、宮中での法要を行う。法皇帰依により、法塔を建て宸筆経を納める。皇后は金襴の袈裟を贈る。第111代・後西院天皇が国師の諡号を贈る。当院7世。桂宮初代・智仁親王、2代・智忠親王、千宗旦らと親交したという。 ◆智仁 親王 安土・桃山時代-江戸時代前期の皇族・智仁 親王(としひと-しんのう、1579-1629)。男性。幼名は六宮・古佐麿(胡佐麿)、八条宮、法号は桂光院。父・誠仁親王(陽光院)、母・新上東門院の第6皇子。第107代・後陽成天皇の弟。幼少で豊臣秀吉の猶子になる。1589年、秀吉に鶴松が誕生したため、猶子を解消し代わりに、1590年、秀吉の奏請により宮家を創立した。当初は八条宮と称した。1591年、親王宣下を受け元服、式部卿に任じられる。1600年、石田三成方の軍勢に囲まれ、丹後田辺城(京都府)に籠城の細川幽斎より、古今伝授(三条西家秘伝、近衛家秘伝、堺伝受)を受けた。1601年、一品に叙される。1615年-1616年、別邸(現・桂離宮)を創設した。1625年、第108代・後水尾天皇に古今伝授を授ける。以来、御所伝授の基になる。51歳。 和歌・連歌を好み、会を催し、和歌などの集書、新写も行った。幽斎に『伊勢物語』などの講釈を学ぶ。別邸は、2代・智忠親王により完成された。 四親王家の一つである八条宮(桂宮)初代になる。墓は桂宮東ノ墓地(上京区)にある。 ◆別宗 祖縁 江戸時代前期-中期の臨在宗の僧・別宗 祖縁(べっしゅう-そえん、1658-1714)。男性。俗姓は佐々木。加賀(石川県)の生まれ。覚雲顕吉の法をつぎ、京都・真如寺などを経て相国寺の住持になる。慈照院9世になる。1682年、朝鮮通信使の随員と本国(圀)寺で筆談唱和した。1711年、朝鮮通信使を大坂まで出迎え江戸まで同行した。57歳。 ◆維天 承瞻 江戸時代前期-中期の臨在宗の僧・維天 承瞻(いてん-じょうせん、1694-1770)。男性。号は松雲。相国寺塔頭巣松軒7世 碩学に選ばれ、1739年、朝鮮修文職に任じられた。1742年、対馬・以酩庵に赴く。1764年、朝鮮通信使に接伴し大坂・江戸を往復した。76歳。 ◆智忠 親王 江戸時代前期の皇族・智忠 親王(としただ-しんのう、1620-1662)。男性。初名は忠仁。父・八条宮智仁親王、母・丹後国主・京極高知の娘・京極常子の第1王子。1624年、第108代・後水尾天皇の猶子になる。1626年、親王宣下、忠仁(ただひと)と称し、後に智忠に改称する。1629年、元服し、中務卿に任じられる。同年、父没後、宮家を継承した。1642年、前田利常の娘・富子を妃にする。後嗣はなく、1654年、後水尾天皇第13皇子・穏仁親王を養子にした。1657年、二品。44歳。 学問を好み、和歌・連歌、書に秀でた。父造営の別荘(桂離宮)を改修し、整備した。 八条宮(桂宮)2代になる。墓は桂宮東ノ墓地(上京区)にある。 ◆広幡 忠幸 江戸時代前期の公卿・広幡 忠幸(ひろはた-ただゆき、1624-1669)。男性。父・八条宮智仁親王、母・京極常子の第3王子。1649年、尾張藩主・徳川義直長女・京姫と婚約、義直の猶子になる。1650年、元服、京姫と結婚し名古屋城へ移る。1660年、京都に戻る。1663年、第112代・霊元天皇より源姓を下賜、臣籍に下る(正親町源氏)。広幡の家号も与えられ初代当主になる。1665年、京都へ戻り、朝廷に出仕、従三位・権中納言、左中将、1667年、正三位、1668年、権大納言に就任した。46歳。 ◆仏像 ◈客殿(本堂)室中の仏間に、本尊「十一面観音立像」、礼の間(北)に中央に「開山像」、広畑家など宮家代々の位牌、右に江戸時代作の8代将軍・足利義政の木像、左に7世・仏性本源国師・昕叔顕啅(きんしゅく-けんたく)を安置する。 ◆建築 ◈書院「棲碧軒(せいへきけん)」は、江戸時代、1629年に建立の桂宮の御学問所を移している。智忠親王が昕叔顕啅に和漢を学んだ礼という。草庵風書院造で、桂離宮古書院と同じ様式になっており、当書院に倣ったといわれている。網代張りの腰高障子、格子の長欄間などが見られる。 ◈「客殿」は、桂宮初代・智仁親王3男・広幡忠幸(1624-1669)が尾張初代藩主・徳川義直(1601-1650)の猶子になったことから、尾張家により江戸時代に建立された。尾州檜の材による。 後に、広幡家により、「玄関」などが拡張されている。 ◆茶室 ◈茶室「頤神室(いしんしつ)」の名は、精神を養うの意味があるという。昕叔顕啅と茶人・千宗旦(1578-1658)の合作により、「宗旦好みの席」とも呼ばれている。 南に庇内土間、四畳半の下座床で、南側に障子二枚引の貴人口のみがある。北西に床の間、炉は中央に切られている。北東に茶道口、二つの下地窓が開けられている。床には宗旦に化けたという衣裳を身に着けた「宗旦狐」の掛軸が掛かる。 南東角に席内の持仏堂である「布袋堂」があり、普段は障子が閉められている。内に布袋像を安置し、像の首は千利休(1522-1591)の首とすげ替えられるようになっていたという。これは、豊臣秀吉により切腹に追い込まれた利休を、密かに祀るための細工だったという。 ◈茶室「棲碧軒」がある。 ◆宗旦狐 宗旦(そうたん)狐にまつわる伝承があり、相国寺には宗旦稲荷社が祀られている。 安土・桃山時代-江戸時代の茶人・千宗旦(1578-1658)は、塔頭・慈照院に茶室を建てた。披露の日、来客があり茶席の時間に遅れた。だが、茶室ではすでに客人が歓談している。宗旦が遅れた詫びを入れると、来客は不審な顔をする。宗旦はすでに点前を済ませ、いま帰ったばかりだという。 その後も、同じようなことが続いた。宗旦はある時、その偽の宗旦に直接問い詰めた。宗旦を名乗る茶人は、自分が境内の薮に住む白狐であること、日頃より宗旦宗匠の茶風に憧れ、その姿を借りて茶に親しんでいたと自白する。また、ある時、偽宗旦は本人の前で点前を披露し、その正体が露見した。だが、宗旦は偽宗旦の見事な点前に感心し、以後、狐を許し可愛がったともいう。 ある時、その狐は猟師に撃たれて死んだという。人々は狐を手篤く葬った。幕末になり、伏見稲荷から神位を受け、慰霊のために境内に社に祀られたという。また、老狐が死ぬ前日、門前の豆腐屋を挨拶に訪れ、主人は好物の油揚げでもてなしたともいう。 慈照院には、宗旦造営という茶室「頤神室(いしんしつ)」があり、宗旦狐の軸が掛けられている。また、窓は狐が逃げ出した際に破ったため、普通のものより大きくなったと伝えられている。 ◆庭園 ◈客殿(本堂)の東、南に表庭が広がる。 表庭(本堂前庭)は、枯山水式庭園であり、庭の北東に比叡山を望む借景庭園になっている。だが、現在、借景はほぼ失われている。苔地に、樹齢300年以上という陸船松(りくせんまつ)といわれるクロマツが植えられている。その枝は低く南に広がり、礼拝石様の平石の上まで延びている。苔地は大海原とも雲海ともいう。その中を風を受けた船が進む様を表すともいう。灯籠、わずかな植栽がある。庭面南端に枯滝石組(神仙石組)、池泉があり、石灯篭がある。本堂より飛石が延びる。方丈落縁の床には、敷瓦、磚(せん)が敷かれ、亀甲型の六角になっている。キリシマツツジが植えられている。 ◈書院の南には露地庭(書院前庭)があり、苔に置かれた飛石は、弧を描いて茶室「頤神室(いしんしつ)」まで延びている。樹齢300年という胡蝶侘助は、小ぶりの花片に白と赤が混じる。手水鉢は長方形に楕円形の水穴が穿たれている。石灯籠が立つ。 ◆朝鮮通信使・以酊庵輪番 江戸時代、朝鮮通信使(1607-1811)は、朝鮮王朝による江戸幕府への12回にわたる外交使節の派遣だった。豊臣秀吉による朝鮮出兵後の修復のために、対馬藩を通じて修復された。将軍の代替わりに際し、祝賀の意味があった。正使、副使のほか、通訳、軍官、画家、医者、料理人、芸能者なども随行し、総勢で400-500人にもなった。海路で釜山を発ち、対馬、相島(あいのしま)、下関、鞆の浦、陸路で大坂、京都、静岡、江戸、時に日光まで足を延ばした。 日本訪問の際に、対馬では「対州修文職(たいしゅう-しゅうぶんしょく)」が外交文書の起草、翻訳、検閲、接伴などに当たった。それらは「以酊庵(いていあん)輪番」と呼ばれ、南禅寺を除く京都五山の4寺の碩学僧侶が、1人ずつ2年交代で派遣されていた。その数は126番、88人になったという。 当院からも通算で5人が遣わされている。そのうち第9世・別宗祖縁(1658-1714)は、第7回(1682年)、第8回(1711年)に派遣されている。第8回の際には大坂から江戸まで往復随行した。また、は、1764年に維天承瞻(いてん-じょうせん、1694-1770)、侍者・月洲周宏(1739-1764)は大坂・江戸まで往復接伴した。 江戸時代後期、1811年に対馬での易地聘礼(えきち-へいれい)が行われた。最後の朝鮮通信使になる。対馬府中には佐賀藩儒者・古賀精里(1750-1817)など多くの文化人が集められ、朝鮮通信使との詩文唱酬が行われている。この時、使節が書き残した多くの詩文・絵画が慈照院に残されている。 ◆文化財 ◈足利義政の遺品。江戸時代の木造・「足利義政像」(70㎝)がある。 ◈平安時代初期作の「灰釉四足壷」(重文)は、織田有楽斎が寄進したという。 ◈鎌倉時代作の絹本著色「二十八部衆像」2幅(重文)。室町時代、牧松筆、紙本墨画「達磨像」(重文)。南北朝時代作の東林筆、絹本著色「地蔵菩薩像」。室町時代作の墨書「慈照院殿諒闇摠簿」(重文)。14世紀後半の絹本著色「無学祖元像」(112×51.2㎝)。 ◈狩野派のものという「桜図屏風」「梅図屏風」がある。 ◈江戸時代、朝鮮通信使の関連資料がある。江戸時代中期、1711年、正使・趙泰億、従事官・李(南岡)邦彦、別宗祖縁和尚の交わした朝鮮料紙に記された書跡、祖縁に贈られた「洪世詩稿(天和度)」、通信使が祖縁に贈った巻物詩文「韓客詞章(正徳度)」(朝鮮通信使図資料として世界の記憶[世界記憶遺産]登録)、ほかの詩文、遺墨、絵画資料などがある。 ■紙本墨書「野馬図」は、伝画・李起龍とされる。賛・朴安期。金明国とともに来日した。柳下に馬が描かれている。軸装52.3×34.7㎝。 ■墨蹟「韓客詞章」巻子4巻は、江戸時代中期、1711年に趙泰億らによる。35×1510㎝、36.5×1026㎝、39.5×1025㎝、43×790㎝。 ◈現代、1982年、住職・久山隆昭が土蔵より襖4枚に貼られた大量の漢詩文を発見した。江戸時代後期、1811年、最後の朝鮮通信使より当寺に贈られたものだった。詩文墨蹟34枚、絵図15枚(「海老図」「竹虎図」「松鷹図」「蘭図」など)、短冊・扇面・花形朝顔の切紙、絹本「竹墨図」など。 現在は、屏風に仕立てられている。紙本墨書・墨画・絹本墨画「詩文絵画貼交屏風」二曲一双、江戸時代後期、1811年、秦東益ほか。 ◆墓 ◈八条宮智仁親王(1579-1629)、八条宮智忠親王(1620-1662)など、桂宮家、広幡家累代の墓所になっている。 ◈寺に隣接している「桂宮東ノ墓地」に宝篋印塔が立つ。安土・桃山時代-江戸時代の誠仁親王第6皇子・智仁(としひと)親王(1579-1629)、江戸時代の八条宮智仁親王第1王子・智忠(としただ)親王(1619-1662)、第108代・後水尾天皇皇子・穏仁(やすひと)親王(1643-1665)、智仁親王妃・常照院(じょうしょういん)、第111代・後西天皇皇子・長仁(おさひと)親王(1655-1675)、後西天皇皇子・尚仁(なおひと)親王(1671-1689)、第112代・霊元天皇第10皇子・作宮(さくのみや、1689-1692)など7墓がある。 ◈「桂宮西ノ墓地」に宝篋印塔が立つ。江戸時代の第112代・霊元天皇第7皇子・京極宮文仁親王(第6代)(1680-1711)、家仁親王妃・基子、公仁親王妃・室子女王(しつこ)、文仁親王第1王子・家仁(やかひと)親王(1703-1768)、家仁親王の第1王子・公仁(きんひと)親王(1733-1770)、公仁親王妃・寿子(ながこ)、第119代・光格天皇の第4皇子・盛仁(たけひと)親王(1810-1811)、第120代・仁孝天皇皇子・節仁(みさひと)親王(1833-1836)など8墓がある。 足利義政の遺骨 大智院→大徳院(慈照院に改め) 足利義視の遺骨 大徳院→大智院 *普段は非公開。5人以上で事前申し込みにより拝観も可。 ❊建物内、一部の建物は撮影禁止。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の駒札、朝鮮通信使ゆかりの地の駒札、『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『拝観の手引』、『京都古社寺辞典』、『京の禅寺を訪ねる』、『第47回京の冬の旅 非公開文化財特別公開ガイドブック』、『京都秘蔵の庭』、『朝鮮通信使と京都』、『講座・人権ゆかりの地をたずねて 2005年講演録』、『京の寺 不思議見聞録』、『週刊 京都を歩く 32』、ウェブサイト「高麗博物館」、ウェブサイト「多胡碑の朝鮮への流伝に関する新資料」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |