|
|
|
| 文覚町 (京都市下京区) Mongaku-cho |
|
| 文覚町 | 文覚町 |
 |
 |
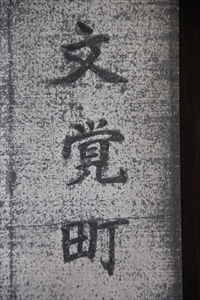 「文覚町」の住所板  文覚町に残る町家  文覚が投獄された牢跡の伝承のある家 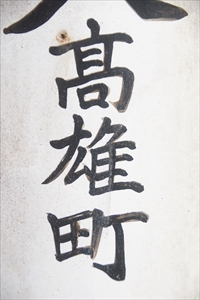 「高雄町」の住所板 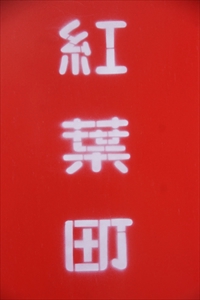 「紅葉町」の町名 |
東中筋通七条に「文覚町(もんがく-ちょう)」の地名がある。周辺には文覚ゆかりの「高雄町」「紅葉町」も見られる。 かつて付近に、平安時代後期-鎌倉時代初期の僧・文覚が投獄されたという牢があり、地名の由来になったという。 また、平安時代に一帯は、第58代・宇多天皇の御所「亭子院(ていじ-の-いん)」が営まれていた。 ◆歴史年表 平安時代、この地は、平安京条坊の左京七条二坊三保十三町にあたった。 903年、町全域が第58代・宇多天皇の中宮・藤原温子(872-907)の邸になった。「東七条宮」と呼ばれたと記されている。(『日本紀略』) 907年、温子の没後、宇多上皇(867-931)の御所「亭子院(ていじ-の-いん)」になる。(『拾芥抄』) 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、西本願寺の寺内町になる。寺内九町組のうちの学林組に属した。 江戸時代、1637年、「天使突抜(てんし-つきぬけ)四丁目」と記されている。(「洛中地図」) 1665年、「もんがくの町」とある。町名の由来は、文覚を投じた牢跡に因むという。(『京雀』) 1786年、「東中筋四丁目」と記されている。(「京都洛中洛外絵図」) ◆藤原温子 平安時代前期-中期の女御・藤原温子(ふじわら-の-おんし/よしこ、872-907)。女性。七条中宮、東七条院、東七条皇后、七条后。父・藤原基経(もとつね)、母・操子女王の3女。887年、基経と第59代・宇多天皇との間に起きた基経の参内拒否事件の阿衡(あこう)の紛議(阿衡事件)の収拾策として、888年、入内し第59代・宇多天皇の女御になった。890年、均子内親王を産む。893年、正三位。897年、宇多天皇の譲位により、第60代・醍醐天皇(実母・胤子)の継母として、皇太夫人になり中宮と称した。905年、病により出家した。36歳。 東五条堀川院、朱雀院、東七条宮などに住む。和歌に優れ、歌壇の中心になる。歌人・伊勢は温子の女房だった。 深草山で火葬され、陵所は宇治陵(宇治市)になる。 ◆宇多天皇 平安時代前期-中期の第59代・宇多天皇(うだ-てんのう、867-931) 。男性。定省(さだみ)、亭子院帝(ていじいん-の-みかど)、寛平(かんぴょう)法皇。京都の生まれ。父・第58代・光孝天皇、母・尊称皇太后・班子(はんし)女王(式部卿・仲野親王の娘、第50代・桓武天皇の孫)の第7皇子。884年、源姓により臣籍に下り、官人になる。887年、病の父・光孝天皇の希望、太政大臣・藤原基経の推挙により親王に復した。その初例になる。皇太子、践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)、即位した。その後、基経との間に権力争いが起こる。勅書中、橘広相が起草した「阿衡の任」の解釈をめぐり、基経は「実権のない礼遇」として天皇に抗し政務を怠業する。半年後、天皇が譲歩し勅書を改めた。(「阿衡(あこう)事件」)。891年、基経の没後、関白を置かず、基経に諫言した菅原道真、基経の子・藤原時平を起用する。897 年、13歳の皇太子・敦仁(あつひと/あつぎみ)親王(第60代・醍醐天皇)に譲位し、帝王学の訓戒「寛平御遺誡(ごゆいかい)」を与え、道真の重用を求めた。太上天皇と称せられる。899 年、仁和寺で出家(空理、後に金剛覚)、仁和寺1世になる。太政法皇になり、出家した上皇を「法皇(太上法皇)」と称した初例になる。仁和寺内の御所が「御室」と尊称された。東大寺で菩薩戒、901年、東寺で伝法灌頂を受ける。道真は時平の讒言(ざんげん)により太宰府へ左遷になる。宇多法皇は内裏宮門に座り込み抗議した。913年、詩宴「亭子院歌合」を開く。沈滞していた詠歌への意欲を刺激した。918年、仁和寺1世になる。大覚寺で寛空に灌頂を授けた。 基経の死後は藤原氏を抑え、菅原道真を起用した。摂関政治の弊害を改める親政を行う。律令の原則に立ち返る。(「寛平(かんぴょう)の治」)。仁和寺内に御所を営み、亭子院、六条院にも住む。和歌、音楽を好み、琵琶の名手として知られた。歌集『亭子院御集』、『古今集』などにも収められた。天皇日記の初例『宇多天皇日記』を著す。寺家宝蔵目録『仁和寺御物実録』がある。京都で没した。65歳。 仁和寺御室で没し、境内北の大内山陵(北区)に葬られた。 ◆文覚 平安時代後期-鎌倉時代前期の真言宗の僧・文覚(もんがく、1139-1205)。男性。俗名を遠藤盛遠(もりとお)。「荒法師」といわれた。摂津国(大阪府・兵庫県)の武士の家に生まれる。幼くして両親を失う。摂津源氏傘下の摂津国・渡辺党の武士で、上西門院(第74代・鳥羽天皇皇女)に仕える北面の武士になる。1159年、18歳で従兄弟で同僚の渡辺渡(わたる、渡辺左衛門尉源渡)の妻、袈裟御前に横恋慕し、誤って殺したことから出家し、文覚と称した。那智、熊野で修行する。荒廃していた神護寺に入り、1173年、再興のために、第77代・後白河天皇に勧進を強訴し、不敬罪で伊豆国に配流された。その地で知り合った源頼朝に平家打倒の挙兵を促したという。盛遠は、密かに京都に戻り、後白河院の院宣を得て頼朝に伝えた。1192年(1185年)、鎌倉幕府成立後、頼朝、後白河院の庇護を受ける。神護寺再興を果たし、東寺 高野山などの修復も手がけた。頼朝の死後、1199年、後鳥羽上皇(第82代)により佐渡国へ再び流罪となる。一度許されて京都に戻る。1205年、謀反を疑われ三度目となる対馬に流され客死した。65歳。 弟子に神護寺復興を継いだ上覚、孫弟子に高山寺開山の明恵らがいる。 ◆亭子院 邸宅「亭子院(ていじ-の-いん)」は、平安京の左京、七条坊門小路の南、油小路の東にあった(『二中歴』)。七条坊門南・西洞院西の2町にあったともいう(『拾芥抄』) 平安時代前期-中期の第58代・宇多天皇中宮・藤原温子(872-907)の邸であり、「東七条宮」と呼ばれていた。(『日本紀略』)。 平安時代前期、907年の温子の没後には、宇多上皇(867-931)が住み、「亭子院」と称された。(『拾芥抄』)。上皇の通称にもなった。 ◆文覚町 文覚町は、南北の北小路通を挟み、町北には東西の北小路通(旧・北小路)がある。 江戸時代前期、1637年に、この地の地名は「天使突抜(てんし-つきぬけ)四丁目」と記されている。(洛中地図)。1641年以前には、「天使のつきぬけ尻」とある。(「平安城町並図」) 1665年には、「もんがく町」の地名が記されている。文覚は「一院(後鳥羽院)の御遊をさまたげ奉り、からめとられて土の牢に百日入をかれ、それより流されて伊豆の大島にすてられ、兵衛佐頼朝(源頼朝)にむほんすすめたりける、此の町はその時の牢屋あと也」とある。(『京雀』)。この頃、もんがく町などの町名も併用されていたとみられる。 平安時代後期、1173年に、文覚は神護寺(右京区)再興のために、第77代・後白河天皇に勧進を強訴し、不敬罪で伊豆国に配流された。1199年には、後鳥羽上皇(第82代)により、佐渡国へ再び流罪になった。文覚は、捕えられ土の牢に100日入れられたという。その牢がこの地にあったという。 文覚町には、牢跡と伝えられる家が残されている。中には井戸跡もあるという。また、文覚町の北には「高雄町(たかお-ちょう)」「紅葉町(もみじ-ちょう)」の地名も残り、いずれも文覚に関わる同じような伝承があり、地名の由来になったという。(『京雀』『山州名跡志』『坊目誌』) なお、江戸時代中期、1786年には付近は「東中筋四丁目」と記されている。(「京都洛中洛外絵図」) ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都市の地名』、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |