|
|
|
| 岩倉具視幽棲旧宅 (京都市左京区岩倉) Former Residence of Iwakura,Tomomi |
|
| 岩倉具視幽棲旧宅 | 岩倉具視幽棲旧宅 |
 |
 |
 表門  表門、石標  通用門  通用門   主屋  中門  主屋、式台、玄関  主屋  主屋、茅葺屋根  主屋、次の間  主屋、次の間のガラス障子  主屋、座敷  主屋、沓脱石  主屋前の庭  主屋前の庭  主屋前の庭、鉄燈籠  主屋の庭、鉄燈籠  繋屋  繋屋  附属屋、右は繋屋  附属屋、勝手口  附属屋、勝手口のポンプ  附属屋、炊事場  附属屋、炊事場の竈  附属屋、居室  附属屋、遣り掛  附属屋、台所  附属屋、居室  主屋、繋屋、附属屋の間の中庭  中庭 |
東に比叡山を望む洛北・岩倉に、幕末より近代に活躍した政治家・岩倉具視が5年間を過ごした岩倉具視幽棲旧宅(いわくらともみ-ゆうせい-きゅうたく)(国指定史跡)が公開されている。 ◆歴史年表 江戸時代、1825年、9月、生後間もない岩倉具視は、岩倉花園村の山本九兵衛宅に預けられる。 近代、1862年、9月、具視は、朝廷内攘夷派の台頭により辞官し、落髪、蟄居した。霊源寺、西芳寺を経て、洛中からの追放令により失脚した。10月、当初は、洛北・岩倉村の藤屋藤五郎の廃屋を借りて幽棲した。具視の次男・具定を里子として預っていた農夫・三四郎の世話による。藤五郎は当初、具視に家を貸すことに難色を示したため、実相院門跡・坊官芝昇澄が藤五郎の説得に入る。 1863年、具視宅に「四奸」の一人、千種有文の家臣・賀川肇の斬り落とされた腕が届く。具視は刺客に狙われ、岩倉花園村の山本九兵衛宅に一時隠れた。 1864年、具視は、大工・藤吉の居宅(現在地の附属屋)を購入し移り住む。その後、現在の主屋と繋屋を増築した。 1865年、尊攘派の志士、松尾相永、藤井九成が訪れる。次第に反幕府的王政復古論に傾く。 1867年、坂本龍馬、中岡慎太郎、大久保利通、品川弥二郎らが居宅を訪れ、具視と密議を行った。11月、具視は、洛中帰洛を許される。 1877年、具視が生前に岩倉村に寄付した300円の記念事業により、金井谷池(権土地)、花園のはぶ池が造られる。 1902年、附属屋の屋根の一部が茅葺より瓦葺に改築された。 1928年、武田五一の設計により現在の対岳文庫が建てられる。 1932年、敷地が国指定史跡になる。 現代、2007年、対岳文庫は国の登録有形文化財に指定された。 2008年-2012年、京都市により旧宅などの修理が行われた。 2013年、1月、旧宅を長年にわたり維持・管理、公開してきた財団「岩倉公旧蹟保存会」の解散に伴い、保存会は旧宅を京都市に寄付した。以後、旧宅は京都市による維持・管理になる。5月、一般公開が始まる。 ◆岩倉具視 江戸時代後期-近代の公卿・政治家・岩倉具視(いわくら-ともみ、1825-1883)。幼名は周丸(かねまる)、号は華竜、対岳、法名は友山。京都の生まれ。父・前権中納言・参議正三位・堀河康親(やすちか)の次男。1838年、公卿・岩倉具慶(ともやす)の養子になり具視と称した。従五位下に叙せられ、昇殿を許された。1853年、関白・鷹司政通により歌道を学ぶ。1854年、第121代・孝明天皇の侍従、従四位下になる。1857年、天皇近習になる。1858年、日米修好通商条約締結に反対し、維新公卿88人で参内して抗議した。(「廷臣八十八卿列参事件」)。意見書「神州万歳堅策」を孝明天皇に内奏する。1860年、公武合体派として、天皇の妹・和宮の将軍家降嫁の上申書を提出する。1861年、正四位下、和宮に随行し江戸へ向かう。1862年、朝廷内攘夷派の台頭により具視は佐幕派と見做される。「四奸二嬪」とされ弾劾により辞官し、落髪、蟄居した。霊源寺、西芳寺、岡崎・永陽庵(井窪寺)を経て、洛中よりの追放令で岩倉村に移る。1865年、公卿・中御門経之、薩摩・水戸・土佐藩士と交流した。1866年、近衛忠煕の復職に働き、幕命により桑名藩に監視下に置かれる。1867年、洛中帰洛を許され、王政復古に尽力した。1868年、明治新政府の議定兼輔相に就く。1871年、外務卿、右大臣、特命全権大使として欧米歴訪(岩倉使節団)した。1873年、太政大臣代理になり、西郷隆盛の征韓論を排した。1874年、赤坂喰違坂で暴漢に襲われ負傷する。1880年、伊藤博文は大隈重信解任と国会開設の勅諭了承を具視に求め、具視は大隈を罷免する。(明治十四年の政変)。1883年、京都御所保存の計画を立てたが、病により東京で没した。59歳。 正一位太政大臣を追贈。「維新十傑」に数えられた。日本初の国葬が執り行われた。 ◆岩倉槇子 江戸時代後期-近代の女性・岩倉槇子(いわくら-まきこ、1827-1903)。父・大津の膳所藩勘定組・野口為五郎賀代の次女。兄の賀柔が岩倉具視に仕え身辺警護に当たる。槇子は具視の身の回りの世話をした。岩倉が志士に追われた際に膳所の実家に匿う。具視の密書を兄とともに京都に届けた。1874年、具視の正室・誠子没後、継室になり二男三女をもうけた。77歳。 墓は東京・海曇寺にある。 ◆岩倉具定 江戸時代後期-近代の政治家・岩倉具定(いわくら-ともさだ、1852-1910)。京都の生まれ。父・岩倉具視、母・野口槇子の第3子(次男)。1868年、戊辰戦争勃発後、東山道先鋒軍総督として転戦した。1870年、アメリカ合衆国に留学する。帰国後は政府に出仕した。1882年、伊藤博文の憲法調査に欧州随行する。1884年、岩倉家の家督を継ぎ、公爵。帝室制度取調委員、貴族院議員、学習院院長。1900年、枢密顧問官、1909年、宮内大臣。57歳。 ◆岩倉具経 江戸時代後期-近代の政治家・岩倉具経(いわくら-ともつね、1853-1890)。父・岩倉具視、母・野口槇子の3男。1868年、戊辰戦争で東山道鎮撫副総督(総督は兄・具定)として江戸へ進撃、江戸開城後、奥羽征討白川口副総督(総督・兄具定)、兄と共にすぐに辞した。1870年、兄と共に米国へ留学する。1878年、帰国し、太政官、大蔵省、外務省勤務した。1884年、男爵、外務書記官として駐ロシア日本公使館、1888年、帰国後北白川宮別当、帝室制度取調委員、宮中顧問官を歴任した。38歳。 ◆松尾多勢子 江戸時代後期-近代の女性・松尾多勢子(まつお-たせこ、1811-1894)。信濃国(長野県)の生まれ。父・豪農・竹村常盈(つねみつ)の長女。1829年、庄屋・松尾左次右衛門元珍に嫁ぐ。10人の子を育てた。平田国学に傾倒し、1862年、52歳で単身上洛し、平田門下の京染取次商「伊勢久」池村久兵衛の世話になる。岩倉具視の密偵になり、具視が王政復古を目指していることを報告した。1863年、木像首梟事件後、京都を脱した。1868年、鳥羽・伏見の戦いで上京し、子、孫を征討軍に従軍させ、自らは岩倉邸で家政をする。1881年、一度、東京へ出る。その後、故郷に戻り、余生を送った。具視は生涯、命の恩人として遇した。84歳。 ◆武田五一 近代の建築家・建築学者・武田五一(たけだ-ごいち、1872-1938)。備後福山(広島県)の生まれ。父・備後福山藩士・司法官・平之助(直行)、母・八重の第5子。父の赴任に従い、神戸、姫路、岐阜、高知に住む。1888年、京都第三高等中学校補充科に入学した。1894年、京都第三高等中学校本科を卒業し、京都帝国大学工科大学造家学科に入学する。1897年、帝国大学(東京帝国大学)造家学科(建築学科)を首席卒業し、同大学院に進学した。1899年、大学院中退後、東京帝大助教授に任じられる。東京高等師範学校講師嘱託、東京美術学校教官になった。1901年-1903年、文部省より命ぜられ欧州留学する。ロンドン・カムデン美術学校で学び、各地を巡る。アール・ヌーボー、セセッションなどを体験する。1903年、帰国後、京都高等工芸学校(現・京都工芸繊維大学)図案科教授になる。1904年、京都府技師を兼任し、平等院鳳凰堂・鹿苑寺金閣の保存に関わる。1907年、東京・福島行信邸で、日本初のウィーン・セセッションの様式を試みた。アール・ヌーボーの造形を紹介する。1908年、大蔵省臨時建築部技師を兼任し、国会議事堂建築のために欧米視察した。1912年、パナマ太平洋万国博覧会事務取扱嘱託になる。1915年、工学博士学位を取得する。勲四等瑞宝章を受賞した。1916年、法隆寺壁画保存会委員になる。1917年、片岡安らと「関西建築協会」を設立する。1918年、名古屋高等工業学校(現・名古屋工業大学)校長に転任した。1920年-1932年、京都帝国大学建築学科創立に伴い教授になる。1925年、大蔵省営繕管財局技師を兼任した。1929年-1931年、京都帝国大学営繕課長事務取扱として学内建築物の造営に関わる。1931年、欧米出張し、19カ国を訪れた。1934年以来、法隆寺大修理工事事務所長を務める。65歳。 「関西建築界の父」といわれた。奈良・京都の古社寺保存修復、橋梁、博覧会場、公園、記念碑、都市計画、街路施設、家具意匠、染色なども手掛けた。主な作品として、旧日本勧業銀行本店(1899) 、日本初のセセッション建築とされる東京・福島邸(1907)、京都府立図書館(1909)、京都・円山公園(1912)、京都・同志社女子大学ジェームス館 (1913) 、京都・旧松風嘉定邸 (現・五龍閣、1914)、山口県庁舎・県会議事堂(1916) 、大阪・瀧安寺鳳凰閣(1917) 、兵庫・清水寺根本中堂・大講堂・本坊・客殿(1917) 、東京・旧村井吉兵衛邸(現・延暦寺大書院、1919) 、 兵庫・清水寺鐘楼 (1919)、兵庫・光明寺根本本堂(1925) 、 和歌山・高野山大学図書館 (1928)、代表作の東方文化学院京都研究所(1930)、京都・同志社女子大学栄光館(1932) 、鳥取・三朝大橋(1934年) など多数。葵橋、賀茂大橋なども設計した。 ◆建築 敷地(1553㎡)は、ほぼ方形になっている。敷地の南に南土塀が築かれ、西よりに表門が開く。東に通用門が設けられ、見学者はここより入る。表門より母屋に向かう小石を敷き詰めた小道が付けられている。右手に中門があり、主屋、南庭に通じる。 居宅は南の茅葺の主屋(60㎡)と、その北の桟瓦葺の附属屋(67㎡)、二棟の間を繋ぐ繋屋(9㎡)があり、いずれも簡素な造りになる。 ◈「主屋(鄰雲軒、りんうんけん)」は、当初からのものではなく、江戸時代、1864年の増築により建てられた。東西棟で西側に式台を設けている。玄関、その奥に次の間(6畳)、床の間、床脇、天袋、地袋のある座敷(6畳)が東へと続いている。座敷には具視の孫・東伏見宮妃周子(かねこ、1876-1955)書の「鄰雲軒」の額が掲げられている。南に手延ガラスを使用したガラス障子が立てられており、当時としては珍しいという。北と南側に縁側を設け、中庭、南の庭に面している。 ◈「繋屋」も後の増築による。浴室、便所が設けられ、東に縁がある。 ◈北の「附属屋」は、当初よりあり、西の勝手口より入ると炊事場、台所がある。東、南に3室の居室(4畳半)がある。東と南に縁を廻し、南は中庭に面している。 ◈敷地の東北にある洋館「対岳文庫(たいがく-ぶんこ)」(国登録有形文化財)は、1928年に岩倉具視の遺品を収蔵陳列するためらに建てられた。建築家・武田五一の設計による。1929年に東伏見宮により対岳文庫と名付けられた。具視の雅号「対岳」に因み、また、比叡山と対峙する岩倉村を表している。 主屋に切妻妻入の玄関を南側に突出し、外壁上部は腰の部分はモルタル洗い出し仕上げ、上部はスクラッチタイル貼(タイル表面を櫛引きとし、平行の溝とした粘土タイル)になる。扉上部はアーチ型になっており、鉄格子にガラス板が嵌められている。内部は、陳列室と収蔵室があり床板敷、板張の壁になる。鉄筋コンクリートの梁が渡されている。 施工は小嶋田中工務店、鉄筋コンクリート造、平屋建、桟瓦葺。 ◆庭園 主屋の南に、岩倉具視の手植えという松の大木が植えられている。石段を通用門へ降りると池が造られ、楓なども植えられている。 主屋と附属屋の間にある中庭に、簡単な石組みがある。 ◆文化財 敷地内の「対岳文庫(たいがくぶんこ)」には、岩倉具視遺品類、明治維新関係文書などの一部を展示・収蔵している。 現在、「岩倉具視関係資料」(重文)1011点、「岩倉具視関係資料」(京都市指定有形文化財)109点は、京都市歴史資料館(上京区)に収蔵されている。 「岩倉具視関係資料」(江戸時代-明治期)は、岩倉具視の書状、記録、詠草、遺品、伝記編纂関係資料などによる。著作『叢裡鳴虫(そうりめいちゅう)』は、1865年頃の幽居中に書かれた。1871年-1873年の欧米歴訪の際の書簡集「万里風信(ばんりふうしん)」は、遣外使節の実情を記した。1869年-1875年に子・具綱宛の書簡「長閑玉章(ちょうかんぎょくしょう)」。 「岩倉公関係文書」30巻には、著作「神州萬歳堅策(しんしゅうばんざいけんさく)」、日記、自筆書状、意見書、建議案、書簡、建白書がある。 遺品には、幽居中に使用していた日用什器類、1874年に旧土佐藩士族に襲撃された「赤坂喰違事件」で身に付けていた紋羽織、袴、紋服、角帯、脇差、そのほか、遣外使節団として訪欧した際に入手した懐中時計などがある。 「伝記編纂関係資料」は、1906年に刊行された『岩倉公実記』に関連した資料であり、1883年の岩倉没後、勅命により編纂着手された。 木戸孝允(桂小五郎)、坂本龍馬、三条実美などの遺墨、遺品などもある。 ◆墓 主屋の東に岩倉具視遺髪碑、その右脇に継子の槇子(1827-1903)夫人の碑が立つ。 遺髪碑の北に次男・岩倉具定(ともさだ、1852-1910)、3男・岩倉具経(ともつね、1853-1890)の碑が立つ。 ◆年間行事 岩倉具視遺髪碑慰霊祭(7月20日)。 岩倉具視の古文書を読む講座(毎月第4土曜日)。 *対岳文庫内の撮影禁止 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 京都市パンフレット、『京都府の歴史散歩 中』、『洛北岩倉誌』、『京都隠れた史跡の100選』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『おんなの史跡を歩く』、『女たちの京都』、『京都歩きの愉しみ』 、『武田五一の建築標本』、『京都の洋館』、ウェブサイト「コトバンク」  |
 対岳文庫 |
 対岳文庫、具視の孫・東伏見宮妃周子筆 |
 対岳文庫 |
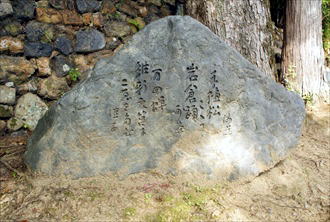 歌碑、(丸山)海道「手植松 こゝに 岩倉踊 かな」、「万の蝉 維新文筥に こゑをたむ」(丸山)佳子 |
 岩倉具視遺髪碑 |
 岩倉具視遺髪碑 |
 岩倉具視遺髪碑 |
 岩倉槇子(1827-1903)の碑 |
 岩倉具定(ともさだ、1852-1910)の碑 |
 3男・岩倉具経(ともつね、1853-1890)の碑 |
 池 |
|
 |
 |
| |
|