|
|
|
| 白峯神宮 (京都市上京区) Shiramine-jingu Shrine |
|
| 白峯神宮 | 白峯神宮 |
 |
 |
   手水舎  手水舎   拝殿  拝殿  本殿    地主社  地主社  伴緒社(伴尾社、とものおしゃ)  伴緒社    潜龍社  潜龍社  潜龍社  潜龍社  潜龍社、祭神は、染、水、醸造の守護神を祀る白峯大龍王・紅峯大龍王・紫峯大龍王。家系の悪縁断ち、厄除、病気平癒、事業繁盛。   潜龍社にある名水「潜龍水」、笑い龍  名水「飛鳥井」  「崇徳天皇欽御之碑」  西村尚の歌碑「小賀玉のしじ葉が もとの 飛鳥井の井筒 むかしの物語せよ」  「蹴鞠の碑」  蹴鞠場   右近の橘   飛鳥井家邸にあった樹齢数百年のオガタマノキ(小賀玉)、名の由来は、招霊(おきだま)が語源ともいう。 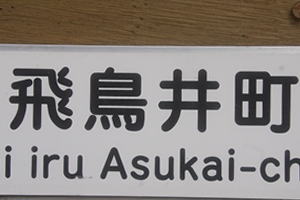 【参照】「飛鳥井町」の地名 |
飛鳥井町(あすかい-ちょう)の今出川通に面して白峯神宮(しらみね-じんぐう)はある。 主祭神は平安時代の第75代・崇徳天皇(すとく-てんのう)、奈良時代の第47代・淳仁天皇(じゅんにん-てんのう)を祀る御霊社になる。旧官幣大社。 球技上達、武道・弓道上達、学芸上達、縁結び、厄除、延命長寿、無病息災、織物和装繁栄、学業成就、水(染、醸造)守護などの信仰がある。 ◆歴史年表 この地には公家・飛鳥井家邸があった。 江戸時代、1866年、第121代・孝明天皇は京都に第75代・崇徳天皇の神霊を迎え祀ろうとして成らなかった。 近代、1868年、9月6日、創建される。飛鳥井家の社地寄進があったという。第122代・明治天皇は、孝明天皇の遺志を継ぎ、12月22日、四国香川の白峰陵墓前の、白峯寺(御影堂)に祀られていた第75代・崇徳天皇の神霊(木像・白峯大権現)を神輿に乗せて当地に遷座した。 1873年、淳仁天皇(淡路廃帝)の神霊が天王森山陵(淡路陵)(南あわじ市)より合祀される。官幣中社になる。 1940年、「白峯神宮」と改称した。官幣大社になる。 ◆崇徳 天皇 平安時代後期の第75代・崇徳 天皇(すとく-てんのう、1119-1164)。男性。名は顕仁(あきひと) 、別名は讃岐院。京都の生まれ。父・第74代・鳥羽天皇、母・待賢門院藤原璋子(藤原公実の娘、白河院養女)の第1皇子。白河法皇(第72代)が璋子に産ませた子ともいう。鳥羽天皇は崇徳天皇を「叔父子(おじご)」と呼んだという。第77代・後白河天皇の兄。1123年、院政をしく曾祖父・白河法皇の意により、5歳で皇位を継承する。父・鳥羽上皇が院政を行う。1129年、白河法皇没後も鳥羽上皇の院政が続く。1140年、源雅定左大将着任をめぐり鳥羽上皇と対立した。1141年、鳥羽上皇に迫られ、3歳の異母弟・体仁(なりひと)親王(第76代・近衛天皇、美福門院得子の所生)が皇位継承する。以後、「新院」と呼ばれ、政令を出す「本院(鳥羽上皇)」との対立激化した。1155年、近衛天皇が急逝後、崇徳上皇は子・重仁(しげひと)親王の即位を望む。だが、異母弟・雅仁(まさひと)親王(第77代・後白河天皇、璋子の所生)が即位し、その子・守仁(もりひと)親王(後の第78代・二条天皇)が立太子となる。1156年、鳥羽法皇没後、崇徳上皇は、左大臣・藤原頼長、源為義、平忠正らと挙兵する。(保元の乱)。この平安時代初の乱に敗れ、讃岐国に配流され、その地で没した。46歳。 日本三大怨霊(ほかに菅原道真、平将門)の一人、天皇初の怨霊(讃岐院怨霊)として恐れられた。和歌に秀で『詞花和歌集』の編纂を命じた。陵墓は火葬所の山陵が白峰陵(しらみねのみささぎ)(香川県坂出市)にされた。没後、1177年、崇徳院の諡号(しごう)を贈られる。1184年、保元の乱の戦場跡、春日河原には粟田宮(左京区聖護院)が建立される。崇徳天皇が流された讃岐の御陵にも、鎌倉時代に御影堂が建立された。堂は白峰寺が管理し、白峰宮と呼ばれる。1868年、京都に白峰宮(白峯神宮、上京区)が建立された。 ◆淳仁 天皇 奈良時代の第47代・淳仁 天皇(じゅんにん-てんのう、733-765)。男性。名は大炊(おおい)王、淡路公、淡路廃帝 。奈良の生まれ。父・舎人(とねり)親王(崇道尽敬皇帝) 、母・当麻山背(たいま-の-やましろ)の第7皇子。第40代・天武天皇の孫。立太子以前に、藤原仲麻呂(恵美押勝)の長子・真従(まより)の未亡人・粟田諸姉(あわだ-の-もろね)を妻とし、仲麻呂の邸宅・田村第に住んだ。757年、第45代・聖武天皇の遺詔により、立太子した道祖(ふなど)王が廃される。道祖(ふなど)王(新田部親王の子)に代わり、仲麻呂の推挙により皇太子になる。758年、第46代・孝謙天皇の譲位を受けて即位した。淳仁天皇は仲麻呂を重用した。太保(右大臣) に任命し、仲麻呂は専権を振るう。太政大臣以下の官名を中国風に改め、国司の任期4年を6年に改める。760年、仲麻呂は万平通宝、大平元宝、開基勝宝などを鋳造し、旧銭(和同開珎)と併用させた。第45代・聖武天皇皇后・光明皇太后の没後、道鏡の処遇をめぐり、762年、淳仁天皇・仲麻呂と孝謙上皇は対立する。上皇は天皇から国家の大事と賞罰の権を奪う。764年、仲麻呂は、上皇の寵を受ける道鏡を廃そうとして乱を起こし、逆賊として追討され敗死した。淳仁天皇も廃帝になり淡路に流され幽閉された。(藤原仲麻呂の乱)。765年、逃走が失敗し、捕えられ亡くなった。33歳。 778年、墓(淡路国三原郡)は山陵扱いの淡路陵(あわじ-の-みささぎ)になる。近代、1870年、淳仁の諡号が贈られる。 1873年、淳仁天皇の神霊が白峯神宮(上京区)に合祀される。 ◆藤原 頼輔 鎌倉時代前期の公卿・歌人・藤原 頼輔(ふじわら-の-よりすけ、1186-1112)。男性。初名は親忠、鼻豊後と称された。父・大納言・忠教、母・賀茂神主成継の娘の4男。藤原師実(もろざね)の孫。山城守、豊後守などを歴任し、1170年、刑部卿、1182年、従三位に至る。後白河院(第77代)の院司別当になった。『千載集』以下に入集、家集『刑部卿頼輔集』。75歳。 蹴鞠の難波・飛鳥井両家の祖になる。藤原清輔家・藤原重家家の歌合などに参加、九条兼実家の歌壇常連で、自邸でも歌合を主催した。蹴鞠は藤原成通に学び秀で「無双達者」とされた。 ◆飛鳥井 雅経 平安時代後期-鎌倉時代前期の公卿・歌人・飛鳥井 雅経(あすかい-まさつね、1170-1221)。男性。藤原雅経。京都の生まれ。父・難波(藤原)頼経、母・源顕雅の娘の次男。兄・宗長(難波流の祖)、妻・大江広元の娘。第82代・後鳥羽天皇の近習になり、第83代・土御門天皇、第84代・順徳天皇の3代、鎌倉幕府にも仕えた。1205年、藤原定家らと『新古今和歌集』撰者の一人になる。参議、従三位に昇る。『新古今集』に入集、家集『明日香井集』 (1292) 、著『蹴鞠(しゅうきく)略記』など。52歳。 飛鳥井家の祖。和歌を藤原俊成に学ぶ。和歌所寄人になった。兄・宗長 とともに蹴鞠 に優れた。将軍・源頼家に厚遇された。 ◆西村 尚 現代の歌人・宮司・西村 尚(にしむら-ひさし、?-2014)。男性。京都府舞鶴市の生まれ。西舞鶴高校在学時から和歌ので評価された。国学院大学大学院博士課程を修了後に帰郷する。福田栄一に師事した。1995年、飛聲短歌会を結成する。第1歌集『少し近き風』を出版した。2012年、最後になった第6歌集「瑞歯(みづは)」を出した。京都市の白峯神宮、朝代神社の宮司を歴任、京都創成大学(現・成美大)で国文学などを教えた。日本文藝家協会と現代歌人協会の会員。飛聲(ひせい)短歌会を主宰した。79歳。 ◆怨霊 平安時代後期、1156年の保元の乱後、奈良時代の第47代・淳仁天皇の淡路配流以来、400ぶりに崇徳上皇は讃岐流罪になった。 上皇は、後生菩提のために血書で大乗経5部を写経し、弟・覚性法親王に送り帰京することを切望した。だが、その望みはかなわなかった。配所での9年の最期は、舌を噛み切り、その鮮血で呪詛の誓文を書き連ね憤死したという。また、写経に血で呪詛の言葉を書き連ね海底深く沈めた。以来、上皇は髪も爪も切らず怨念の鬼と化し、讃岐の地で亡くなったという。(『保元物語』) 讃岐・白峰山への葬列の際には雷雨になり、柩から血が溢れ出たという。その後、京都では火災が相次ぎ、源平の戦乱が起きた。近代に入り、皇都守護のためとして当宮に遷座され、700年の歳月を経て京都に帰郷を果たした。 ◆飛鳥井家・蹴鞠 ◈蹴鞠の起源は、紀元前300年頃の中国、戦国時代の蹴鞠(しゅうきく)にあるという。 日本には、飛鳥時代、538年の仏教伝来により伝えられたという。平安時代中期に、蹴鞠は貴族の遊戯として流行した。その後、公家、鎌倉時代に武士、江戸時代には庶民にも普及する。勝敗を決しない球戯であり、相手に受け取りやすく打ち返した配球を繰り返していく。 蹴鞠の宗家・飛鳥井家は、平安時代末、難波家の忠教(1076-1141)に始まる。藤原氏北家の流れであり難波家の支流、家格は羽林(うりん)家になる。飛鳥井成通(藤原成通、1097-1162)は、蹴鞠名人と謳われ「千日の毬」を達成し、「蹴聖」と呼ばれる。忠教の子・頼輔(1186-1112)は蹴鞠の祖といわれた。その孫・飛鳥井家の祖である参議・雅経(1170-1221)も蹴鞠に長じ、藤原俊成に歌道も学ぶ。2代将軍・源頼家(1182-1204)は飛鳥井流に弟子入りしている。室町時代に、権中納言・雅世(1390-1452)、権大納言・雅親(1417-1490)父子も歌道の発展に尽くした。室町時代-江戸時代に飛鳥井流は次第に衰微する。幕府・朝廷では受け継がれていた。 近代以降、蹴鞠は一時途絶える。第122代・明治天皇の勅命により、1907年/1903年に下賜金を受けて華族らにより蹴鞠保存会が結成された。現代、2001年/2003年に、境内に蹴鞠碑が立てられる。 ◈境内の地主社は、かつて飛鳥井家の邸内社であり、白峯神宮創建の際に遷された。祭神・精大明神(せいだいみょうじん)は蹴鞠の神として祀られている。鞠の精三神ともいう。平安時代後期、第74代・鳥羽天皇の頃(1107-1123)、蹴鞠の名人・飛鳥井成通は、千日の願掛けをし、満願の日に猿に化身した三神が現れたという。このため、鞠を蹴る際には三神の春陽花(やう)、夏安林(あり)、秋園(おう)の神名を掛け声にした。神猿は、当宮と大津の平野神社に祀られている。 ◈飛鳥井流は、右足の甲だけで毬を蹴る。毬の中は空洞になっており、外は2枚の鹿皮を使用し、馬皮の紐で閉じている。毬の直径は20㎝ほどあり、120gの重さがある。境内には鞠庭があり、神が降り立つとされる懸かりの木(式木)(松、桜、柳、楓)が四隅に植えられている。鞠場も設けられ、蹴鞠保存会により蹴鞠(4月、7月)が奉納されている。 ◈現在地には、飛鳥井町の町名が残る。 ◆配流された天皇 配流された天皇としては、当社祭神の奈良時代、第47代・淳仁天皇(733-765)、平安時代後期の第75代・崇徳天皇/年(1119-1164)、そして、鎌倉時代前期、1221年、承久の乱で隠岐に流された平安時代-鎌倉時代の後鳥羽上皇(第82代、1180-1239)の3人になる。 ◆末社 ◈末社・地主社の祭神は、中御前、精大明神(鞠精大明神)、南御前、稲荷神の柊大明神(魔除、厄除、延命長寿)、稲荷神の糸元(いともと)大明神(織物、和装守護)、北御前、今宮大神(無病息災)、白峯天神(学業成就)になる。これらの稲荷神は、かつて飛鳥井家に祀られていた屋敷稲荷神になる。 ◈精大明神は飛鳥井家にあった守護神で、蹴鞠の神になる。スポーツ競技上達、芸能上達の信仰を集める。後鳥羽上皇の建立によるともいう。飛鳥井家が祭祀してきた。 ◈伴緒社(とものおしゃ)の祭神は源為義・源為朝父子になる。ご神体は崇徳上皇筆の二人の画像という。平安時代後期、1156年、保元の乱で崇徳上皇に付いた父・源為義(1096-1156)と、敵対する後白河天皇側に付いたその子・源為朝(1139-1170?)がともに祀られている。二人とも弓の名手とされ武道・弓道上達の神として崇敬された。 ◆建築 ◈神門・拝殿・手水舎・瑞垣は檜皮葺から銅板葺に替わる。 ほか、神饌所、勅使館、斎館、社務所、築地塀などが建つ。 ◈「本殿」は下鴨神社の河合社を模している。流造、銅板葺。 ◆文化財 ◈絹本著色「崇徳上皇像 附絹本著色随身像」1幅(重文)は、鎌倉時代作になる。平安時代後期、1184年に京都に粟田宮の御影堂が建立され、伝えられたものという。江戸時代前期、延宝年間(1673-1681)に安井蓮華光院にあった。(『箱書』)。蓮華光院は粟田宮の真性院と合併しておりその間に蓮華光院に移されたとみられる。崇徳院像の遺例は少ない。崇徳院は坐し笏(しゃく)を持つ。 附随身像2幅は、平安時代後期、1156年の保元の乱の際に上皇方の源為義(1096-1156)像、源為朝(1139-1177)像とみられ立ち姿になっている。室町時代作とみられる。京都博物館保管。 なお、近代、1930年に描かれたとされる写本がある。 ◈崇徳上皇遺愛の「笙」1管、「琵琶」1弦。 ◈刀剣「延寿」は、近代、1877年に奉納された。 ◈薙刀「美濃直胤」は、江戸時代後期、1849年作になる。 ◆樹木 ◈樹齢数100年の小賀玉木(オガタマノキ)(京都市指定天然記念物)は、京都市最大を誇る。飛鳥井家邸宅当時の植栽という。樹高15.7m、胸高幹周は南幹2.42m、北幹2.51m。 ◈含笑花(トウオガタマ)がある。三葉の松(三鈷の松)は、落葉すると黄金色に変わるため、金運ある金銭松ともいわれる。 ◈クロガネモチ、タチバナ、ナギ、リギダマツ、ムクノキ、ムクロジなどがある。左近の桜、右近の橘がある。 ◆小川・名水 神社の東に、かつて「小川(こかわ)」が流れていた。 境内には、名水として知られる「飛鳥井」、「潜龍井(せんりゅうい)」がある。 ◈ 「飛鳥井」は、現代、1985年に地下35mで掘り当てられた。清少納言は『枕草子』中で、京の九名水の一つとして飛鳥井の名を挙げる。168段に「井は、ほりかねの井。走り井は逢坂なるがをかしき。山の井、さしも浅きためしになりはじめけむ。飛鳥井『みもひも寒し』とほめたるこそをかしけれ。玉の井、少将ノ井、櫻井、后町の井。千貫の井。」とある。 平安時代の催馬楽「飛鳥井」には、「飛鳥井に宿りはすべし、や、おけ、蔭もよし、御水も寒し、御秣(みまくさ)もよし」と謡われている。 献茶式(11月23日)では、煎茶道方円流によるお茶が奉献されている。 ◈潜龍社にある名水「潜龍水」は、潜龍大明神の御神体とされる。龍神の坐す潜龍の井から湧くという。家内安全、家業繁栄、悪縁断ち、良縁を得る神徳があるとされる。 ◆御花使 かつて、「文使(ふづかい)」「御花使(おはなづかい)」という祭礼があった。旧暦の7月7日に行われた。近衛家による宮中への暑中見舞いであり、当家の女中が秋の七草を献上していた。江戸時中期、享保年間(1716-1736)に始まったという。その後、中絶し、復活し、再び中断している。 なお、平安時代には、筆頭の公卿が梶の葉に文をしたためた。これを文箱に入れ、女房が御所に遣わされた。文使・御花使は、この暑中の御機嫌伺に由来するという。 使いの女性の井出達は、髪を髷(まげ)に結い、歯は鉄漿(かね、おはぐろ)で黒く染めた。頭に絽の被衣(かつぎ)、白麻の帷子(かたびら)に付帯を締め、黒塗りの高足駄を履いた。手に持つ文箱には暑中見舞いの御文を納めた。供の2者は白丁姿であり、花扇(けせん、扇形の花)を持ち、もう一人はその花扇に朱傘を差して御所に向かった。道中では小町踊が踊られたという。 ◆歌碑 西村尚の歌碑「小賀玉のしじ葉が もとの 飛鳥井の井筒 むかしの物語せよ」がある。 ◆樹木 飛鳥井家邸にあった樹齢数百年のオガタマノキ(小賀玉)がある。名の由来は、招霊(おきだま)が語源ともいう。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、元始祭(1月3日)、節分祭(鬼遣い豆まき神事)・柊大明神例祭(2月節分)、紀元祭(2月11日)、祈年祭(2月17日)、交通安全祈願祭(3月第1土曜日)、春季皇霊祭(3月21日)、春季例大祭・淳仁天皇祭(蹴鞠奉納、蹴鞠体験可)(4月14日)、子どもの日・武道奨励繁栄祭・古武道奉納報告祭(5月5日)、夏越大祓式(茅の輪くぐり神事)(6月30日)、精大明神例祭「七夕祭」・山城舞楽・蹴鞠・小町をどり奉納奉告祭(7月7日)、戦没者慰霊祭(8月15日)、秋季例大祭・崇徳天皇祭(薪能)(9月21日)、秋季皇霊祭(9月秋分)、献燈祭観月の夕べ(10月望月の日)、神嘗祭当日祭・神嘗奉祝祭(10月17日)、伴緒社祭(御弓神事)・七五三詣(11月15日)、新嘗祭(日供講大祭・献茶式・潜龍大明神祭・御火焚祭)(11月23日)、大祓式・除夜祭(12月31日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『伊勢神宮と全国「神宮」総覧』、『京都はじまり物語』、『平安の都』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都のご利益徹底ガイド』、『京都の寺社505を歩く 上』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都時代MAP 平安京編』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 京都を歩く 30 西陣』 、「拝観の手引-令和4年度第58回京都非公開文化財特別公開」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|